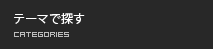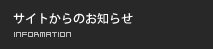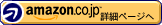プレゼンテーション
経営企画部の人
働き方
起業
ビジネスマナー
マネジメント
ジャーナリスト
学者
ソーシャル
メンター
整理術・時間術
海外
経営
ビジネスモデル
ものづくり
派遣社員
テクノロジー
思考法
コンサルタント
投資
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
常識の中に思考の盲点がある
ライバル車は、エンジンが車体の中心付近に配置され、運転席の後ろにエンジンとミッションが配置されるなど純粋なレーシングカー仕様だった。各社がやっているから、それが「常識」と思いがちだが、その「思考の盲点」にこそ答えが隠れている。その時に探し出した「非常識の本質」は、あえて荷重をかけてタイヤのグリップ力を増やすというものだった。
当時は直列6気筒エンジンの後輪駆動が市販車市場の主流だった。これに対して、V型6気筒エンジンを搭載して、エンジンとトランスミッションの位置と重量でグリップの荷重をコントロールする概念は、未来の技術を使ったものだった。
ル・マンから戻った後、この概念を公式の会議で提案したが、当時の開発担当役員からボロクソに叱咤された。当時は、社内の空気が最も停滞していた時期だった。例えば、マーケットも知らない品質管理の大学の先生が外部から派遣されていた。その先生の許可がないと新規開発ができず、許可される主な要因は「これまで類似の事例があり、実績がある」というもの。中には審査が通りやすいようにトヨタの成功事例をあげてくる者もいた。
1999年、カルロス・ゴーンがやってきた。この新しい流れにより、新しいコンセプトが会社に認知され、2003年に開発をスタートさせた。しかし、いざ会議で提案してみると、役員をはじめ、出席していた全員が大反対という有様だった。誰も「そんなこと、できるわけがない」と見向きもしてくれない。
結局、試作車を社外のメーカーに頼んで独自につくる事にした。試作車が完成し、走らせてみるとポテンシャルの高さがすぐに証明された。ゴーンCEOに「すべてを君に任せる」と言われ、日産GT-Rの開発がスタートする事になった。
当時は直列6気筒エンジンの後輪駆動が市販車市場の主流だった。これに対して、V型6気筒エンジンを搭載して、エンジンとトランスミッションの位置と重量でグリップの荷重をコントロールする概念は、未来の技術を使ったものだった。
ル・マンから戻った後、この概念を公式の会議で提案したが、当時の開発担当役員からボロクソに叱咤された。当時は、社内の空気が最も停滞していた時期だった。例えば、マーケットも知らない品質管理の大学の先生が外部から派遣されていた。その先生の許可がないと新規開発ができず、許可される主な要因は「これまで類似の事例があり、実績がある」というもの。中には審査が通りやすいようにトヨタの成功事例をあげてくる者もいた。
1999年、カルロス・ゴーンがやってきた。この新しい流れにより、新しいコンセプトが会社に認知され、2003年に開発をスタートさせた。しかし、いざ会議で提案してみると、役員をはじめ、出席していた全員が大反対という有様だった。誰も「そんなこと、できるわけがない」と見向きもしてくれない。
結局、試作車を社外のメーカーに頼んで独自につくる事にした。試作車が完成し、走らせてみるとポテンシャルの高さがすぐに証明された。ゴーンCEOに「すべてを君に任せる」と言われ、日産GT-Rの開発がスタートする事になった。
物事に正直に取り組まなければいいものは作れない
「GT-Rの開発は期間3年、スタッフ50名でやります。ヒト・モノ・カネ・時間は従来の半分です」と宣言した。開発メンバーの8割は、経営不振で他社を早期退職した、トラックしか作った事がない連中を引き取った。残りは元々日産にいたアウトロー社員。精鋭は1人もいなかった。
新しいモノをつくろうとする時、本当に求められているのは目的志向のある人材である。他社をリストラされた人は、失うものもなく新しいチャレンジができる。これが人材活用の「非常識な本質」で重要なファクターとなる。
このプロジェクトをスタートさせるにあたって、「正直(事実)」と「基本(本質)」の2つを目標に掲げた。世の中にはやれ会社が決めたから、組織の方針だからと、自分自身に正直に向き合えない場面が多い。しかし、物事に正直に取り組まない限り、良いものは作り出せない。極限まで考え抜いて「非常識な本質」を探し求めようとする時、基本を身に付けておかないと行き詰まる。
新しいモノをつくろうとする時、本当に求められているのは目的志向のある人材である。他社をリストラされた人は、失うものもなく新しいチャレンジができる。これが人材活用の「非常識な本質」で重要なファクターとなる。
このプロジェクトをスタートさせるにあたって、「正直(事実)」と「基本(本質)」の2つを目標に掲げた。世の中にはやれ会社が決めたから、組織の方針だからと、自分自身に正直に向き合えない場面が多い。しかし、物事に正直に取り組まない限り、良いものは作り出せない。極限まで考え抜いて「非常識な本質」を探し求めようとする時、基本を身に付けておかないと行き詰まる。