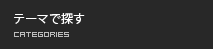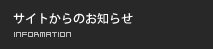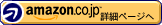-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17

生物はどのように進化するのか
生物はどのように進化するのか、現在までにわかっていることが紹介されている一冊。
■進化にはいまだ謎が残されている
進化とは「生物が世代を継続して変化していくこと」である。従って、もし1つの個体が新しい能力を獲得したとしても、その性質が子や孫といった次の世代の個体に伝わっていかなければ、それは進化とは呼べない。
ダーウィンは人類に進化という概念を示した人物である。しかし現在主流になっている進化論の学説は、ダーウィンが提唱したものとは少し異なっている。現在の進化生物学の標準理論と考えられているのは、ダーウィンの自然選択説と、グレゴール・ヨハン・メンデルの遺伝学説を中心に、いくつかのアイデアを融合させた学説で、これは「ネオ・ダーウィニズム」と呼ばれている。その中核をなす考えは「偶然起こる遺伝子の突然変異が、自然選択によって集団の中に浸透していくことで、生物は進化していく」というものである。
進化という概念は「小進化」と「大進化」の2つに大きく分けられる。小進化というのは、種の枠組みの中で起こる小さな変化である。一方、大進化は種の枠を超えるような、大きな変化のことを言う。そして、小進化の方は遺伝子の変異と自然選択によって概ね説明することができるが、大進化の場合は単純に行かない。
 超短要約
超短要約
実のところダーウィニズムは、種の枠組みを超えるような大進化がどうして起こるのかを解明できていない。同じ遺伝子を持っているからといって、必ずしも形質が同じになるとは限らず、生物の進化は遺伝子だけでは説明できない。
遺伝子は外部の環境によって発現パターンに変化が生じる。この発現パターンが子孫に遺伝することが、進化へとつながる。ただ、問題は「遺伝子の発現パターンが、どのように決まるのか」がよくわかっていない。
近年の研究により、「生物の形を決めるのは、細胞の表面のタンパク質が鍵を握っている」ということがわかっている。細胞の表面は他の細胞と接しているので、細胞の表面のタンパク質は他の細胞との親和性や排斥性に大きな影響を与えている。
多細胞生物は、発生の途中で遺伝子の発現パターンを変化させることで、様々な表面タンパク質を作っていく。表面タンパク質が異なれば親和性の高い細胞の種類も異なるので、形態はダイナミックに変化していき、様々な組織が作られていく。このように表面タンパク質の分布パターンの変動と安定性が、生物の形態を構築していく。現段階では、細胞表面の状況まではわかっていない。
 著者 池田 清彦
著者 池田 清彦
1947年生まれ。生物学者 山梨大学教育人間科学部教授を経て、早稲田大学国際教養学部教授。構造主義を生物学に当てはめた「構造主義生物学」を提唱。その視点を用いた科学論、社会評論なども行っている。
この本を推薦しているメディア・人物
|
作家 養老 孟司 |
章の構成 / 読書指針
| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| まえがき | p.3 | 3分 |  |
| 第1章 ダーウィンとファーブル | p.15 | 12分 |    |
| 第2章 進化論の歴史 | p.37 | 13分 |   |
| 第3章 STAP細胞は何が問題だったのか | p.61 | 14分 |  |
| 第4章 ゲノム編集がもたらす未来 | p.87 | 18分 |      |
| 第5章 生物のボディプラン | p.121 | 11分 |      |
| 第6章 DNAを失うことでヒトの脳は大きくなった | p.141 | 12分 |      |
| 第7章 人類の進化 | p.163 | 13分 |     |
| あとがき | p.187 | 2分 |    |