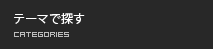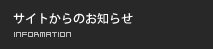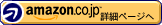経営者
ものづくり
アジア
リーダーシップ
マーケター
20代
接客業の人
法律
商品企画部の人
ソーシャル
文章術・図解術
社会
メーカーの従業員
営業術・交渉術
派遣社員
プレゼンテーション
イノベーション
管理職
経営企画部の人
起業家
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
誰かが書いている場合は読み手でいる
事象と心象が交わるところに生まれるのが随筆である。この定義を見失って映画を評論すると、事象よりに振れてしまえば映画のあらすじばかり書く状態に陥るし、心象よりだと感想だけ書いて終わってしまう。
自分の感想と同じポイントを、誰かの手で自分より豊かな語彙で書かれていたり、自分が感じた疑問点について、なるほどと膝を叩く考察が余すところなく展開されていれば、今更何も書く必要はない。他人と同じことを書いてネットの世界に放流すると、反響は「◯◯さんが言っているのと同じですね」である。
「私が言いたいことを書いている人がいない。だから、自分が書くしかない」というのが読みたいものを書くという出発点である。特段の新しい見方も疑問もなく、読み手で構わないなら、読み手でいればいい。
自分の感想と同じポイントを、誰かの手で自分より豊かな語彙で書かれていたり、自分が感じた疑問点について、なるほどと膝を叩く考察が余すところなく展開されていれば、今更何も書く必要はない。他人と同じことを書いてネットの世界に放流すると、反響は「◯◯さんが言っているのと同じですね」である。
「私が言いたいことを書いている人がいない。だから、自分が書くしかない」というのが読みたいものを書くという出発点である。特段の新しい見方も疑問もなく、読み手で構わないなら、読み手でいればいい。
自分が書いた文章を自分がおもしろいと思えれば幸せ
自分が抱いた心象を自分が読んでおもしろいように書いたところで、誰も読まない。現実は「誰が書いたか」の方が、多くの人にとっては重要である。だからこそ、「ターゲット層にバズりたい」「たくさん読まれたい」という思い違いを捨て、まず、書いた文章を自分がおもしろいと思えれば幸せだと気づくべきだ。それを徹底することで、逆に読まれるチャンスが生まれる。
誰も読んでないといっても、ネット上に文章を置けば、何人かは読んでくれる。書いたものが評判になれば数万人、数十万人が読んでくれるという可能性もないではない。
書いた文章を読んで喜ぶのは、まず自分自身である。満足かどうかは自分が決めればいい。しかし、評価は他人が決める。他人がどう思うかどうかは決められない。
誰も読んでないといっても、ネット上に文章を置けば、何人かは読んでくれる。書いたものが評判になれば数万人、数十万人が読んでくれるという可能性もないではない。
書いた文章を読んで喜ぶのは、まず自分自身である。満足かどうかは自分が決めればいい。しかし、評価は他人が決める。他人がどう思うかどうかは決められない。
物書きは調べることが99%
つまらない人間とは何か。それは自分の内面を語る人である。少しでもおもしろく感じる人というのは、その人の外部にあることを語っているのである。
随筆とは、結局最後には心象を述べるもの。そのためには、事象を提示して興味を持ってもらわなければならない。事象とは、常に人間の外部にあるものであり、心象を語るためには事象の強度が不可欠である。
書くという行為において最も重要なのはファクトである。ライターの仕事はまず「調べる」ことから始める。そして調べた9割を棄て、残った1割を書いた中の1割にやっと「筆者はこう思う」と書く。つまり、ライターの考えなど全体の1%以下で良いし、その1%以下を伝えるために後の99%以上が要る。
調べるに当たっては、一次資料に当たらなければならない。そのためには、図書館を利用し、司書に相談をするのが一番の近道である。
随筆とは、結局最後には心象を述べるもの。そのためには、事象を提示して興味を持ってもらわなければならない。事象とは、常に人間の外部にあるものであり、心象を語るためには事象の強度が不可欠である。
書くという行為において最も重要なのはファクトである。ライターの仕事はまず「調べる」ことから始める。そして調べた9割を棄て、残った1割を書いた中の1割にやっと「筆者はこう思う」と書く。つまり、ライターの考えなど全体の1%以下で良いし、その1%以下を伝えるために後の99%以上が要る。
調べるに当たっては、一次資料に当たらなければならない。そのためには、図書館を利用し、司書に相談をするのが一番の近道である。